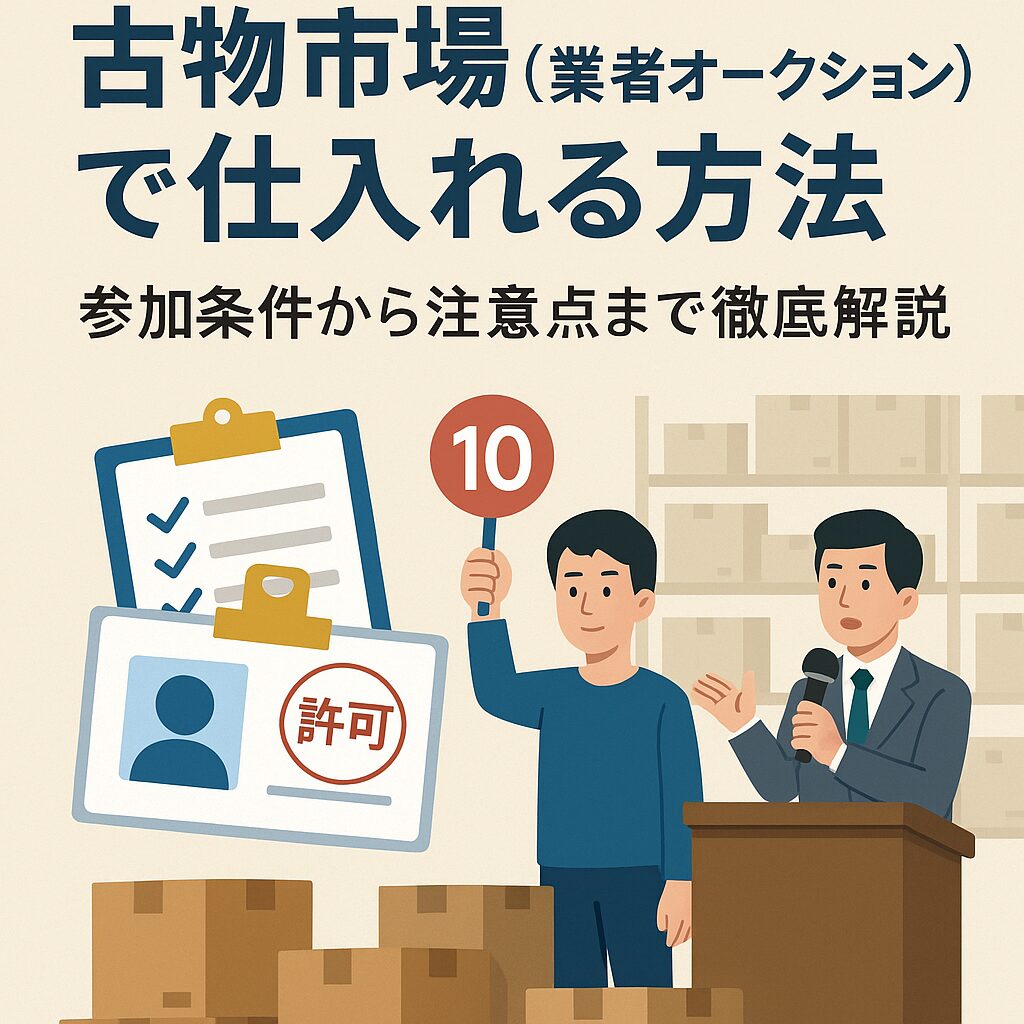転売目的ならオークション出品に古物商許可が必要|申請方法と取得後の注意点
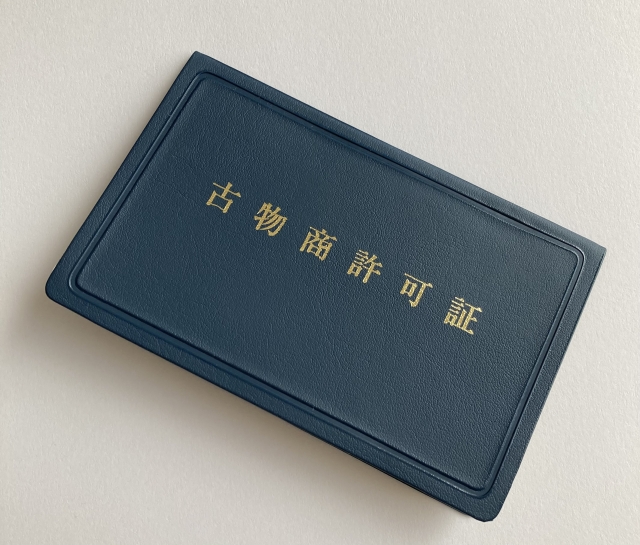
メルカリやヤフオクで不用品を売るだけなら古物商許可は不要ですが、転売目的で仕入れて再販する場合は話が別です。法律上「古物営業」に該当し、許可を取得しないまま続けると罰則の対象になるリスクも。本記事では、古物商許可が必要なケースから申請方法、取得後に気をつけたいポイントまで徹底解説。これから転売を始めたい方や、すでに仕入れを検討している方はぜひ参考にしてください。
なぜ転売(オークション出品)に古物商許可が必要なのか?
転売を副業や本業で考えている人が増えていますが、実は「古物を買い取って売る」行為には法律上の許可が必要です。これを怠ると無許可営業となり、最悪の場合罰金や懲役刑が科されるリスクも。まずはどのような場合に古物商許可が必要になるのかを理解し、安心して転売ビジネスを始めましょう。
古物商許可が必要になるケース
例えばリサイクルショップやフリマアプリ、ネットオークションで安く仕入れ、それを再び売る場合は古物営業法上の「古物商」に該当します。一方、自宅の不用品を処分目的で販売する場合は許可は不要です。利益目的で継続的に仕入れを行うなら、規模にかかわらず許可が必要です。
許可がないとどうなる?罰則やリスク
古物商許可を取らずに仕入れ販売を繰り返すと、古物営業法違反で「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処される可能性があります。さらにプラットフォームの規約違反としてアカウント停止になることも。これを避けるためにも、早めに許可を取得しておくことが大切です。
古物商許可があればできること

古物商許可を取得すると、一般の転売ではできない幅広いビジネスが可能になります。せっかく取得するなら許可を活かし、転売活動をより本格的に展開しましょう。
古物を買い取りして転売できる
中古のブランド品や家電、フィギュアなどを積極的に仕入れ、再販できるようになります。不用品処分とは異なり、仕入れ先を広げて本格的な利益追求ができるのは古物商許可を持つ人の特権です。
古物市場(業者オークション)にも参加可能
さらに古物商許可を持っていると、古物市場(業者限定オークション)に参加できます。一般市場より大幅に安く大量に仕入れられるため、利益率を上げたい人には大きな武器になります。
古物市場(業者オークション)にも参加できるため、さらに仕入れの幅が広がります。
→「古物市場の仕入れ方法はこちら」でリンク。
古物商許可の申請方法と取得までの流れ
古物商許可は各都道府県の警察署を通じて申請します。書類を揃えるだけで難しくはありませんが、一定の費用や審査期間がかかるため計画的に進めましょう。
必要な書類と手続き
主に住民票や身分証明書、略歴書などを準備し、営業所(自宅でも可)の賃貸契約書や配置図も必要です。また管理者講習を受けるケースもあります。
申請から許可が下りるまでの期間と費用
費用は約19,000円(都道府県により異なる)で、申請から許可がおりるまでは30~40日程度が一般的。審査の間も警察署から確認の連絡が入ることがあります。
許可申請の手続き詳細はこちらの「古物商許可の取得完全ガイド」で詳しく解説しています。
許可取得後に気をつけたいこと
古物商許可を取った後もやるべきことは続きます。ルールを守り、スムーズにビジネスを続けるための注意点を押さえましょう。
古物台帳の記載義務とは?
古物商には「台帳(取引帳簿)」を付ける義務があります。誰から何をいくらで仕入れ、誰に売ったのかを記録しておくものです。怠ると監査で指摘される可能性があるため、簡単なExcelやノートで日々記録するのがおすすめです。
許可を維持するための注意点
届出内容(住所や代表者)が変わった場合には速やかな変更届が必要です。また古物市場に参加する際は市場ごとのルールも守りましょう。これを怠ると営業停止や許可取消の対象になります。
また、これから転売を始める方向けに「転売で稼げる商品ランキング」も用意しています。あわせてご覧ください。
まとめ|これから転売を始める方へ
転売で収入を得るなら、古物商許可は避けて通れない重要なステップです。違法にならないよう法律を理解し、申請から台帳管理までしっかり行うことで、安心して転売ビジネスを続けられます。これから仕入れ販売を本格的に始めたい方は、まずは古物商許可の取得を計画しましょう。
★★★買取品を増やしたと考えるショップ関係者様、買取マルシェに掲載しませんか?★★★
まだ記載されていない地域のショップオーナー様は無料登録をご検討ください。
ショップの宣伝は少しでも増やすことが、商売繁盛の上で大切なポイント。
掲載されることで「機会損失」を防ぐことが出来ます